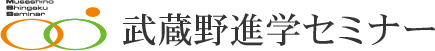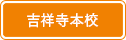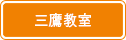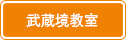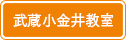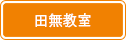フェルマーの最終料理
こんにちは。
吉祥寺の𠮷田です。
この夏、『フェルマーの最終定理』(サイモン・シン著)を読みました。
昨年、沼尻先生にお勧めされて以来、ずっと読みたかった本です。
折しも、アニメ『フェルマーの料理』が7月から放送開始し、そのフェルマーという響きに触発されるかたちで読み始めた格好です。
そして──です。
読み始めてみると、これがまあ、めっぽう面白い!
単に、フェルマーの最終定理を証明するプロセスがエキサイティングというだけでなく、
ピタゴラスに始まる、「数学という営み」の厳密さに終始シビれるのです。
徹底した演繹法!
徹底した基礎づけ主義!
ピタゴラス、ユークリッド、ディオファントス、
フェルマー、ニュートン、オイラー、
ガウス、リーマン、ポアンカレ、、、
連綿と続く数学界の巨人たち!
数学の歴史とは、幾つかの公理の上に、幾千もの定理を積み重ねた、巨大な論理的建造物なのです。
(公理と定理の違いは、ムサシンの身近な数学の先生に訊いてみましょう)
それを体現するかのようなアンドリュー・ワイルズによる130ページにも渡る論証。
そのどこかに、わずかな誤謬も許されないのが数学的証明であり、まるで1ブロック抜けば全てが瓦解する長大なジェンガのようです。
その全てを理解するには、楕円曲線、モジュラー形式、ガロア表現、ヘッケ環、コリヴァギン=フラッハ法、岩澤理論などなど、
複雑難解な概念や方法論の習熟が必要らしいのですが、
何より感動するのは、最終的な証明法が「数学的帰納法」と「背理法」という、
高校数学で習う、我々にとってなじみのある証明法であるということです。
350年もの間、誰も証明できなかったフェルマーの最終定理の証明に、我々でも知っている証明法が、がっつり使われている──
これにはシビれましたよ、ええ、花椒たっぷりの麻婆豆腐みたいに。
【フェルマーの最終定理】
「3 以上の自然数 n について、x^n + y^n = z^n となる自然数の組 (x, y, z) は存在しない」
フェルマーの最終定理が偽だと仮定する(すなわち、フェルマー方程式に解があるとする)
↓
その解は、楕円曲線の方程式に変形できる
↓
しかし、その方程式はモジュラー形式ではありえない
↓
「谷山=志村予想」が真ならば(この証明にワイルズは数学的帰納法を用いました)、すべての楕円曲線はモジュラー形式である
↓
よって、仮定が間違っている
↓
つまり、フェルマー方程式に解はない(すなわち、フェルマーの最終定理は真である!)
この論理的には極めてシンプルな背理法により、3世紀以上も続いた未解決問題は終止符を打たれたわけです。
あーすっきり。
こうして振り返ってみても、やはりその壮大でロジカルな問題解決劇には感動を禁じ得ないのですが、
一方で、ふとこんな疑問が首をもたげます。
人はなぜ、こんなに必死になって、論理的建造物を構築しようとするのか?
数学的地平が広がって、数学の世界がますます豊かになるとか、
物理学へ応用すると、量子の謎や、宇宙の謎がまた一つ解明されるとか、
なんかそういう理由付けは、尤もらしくはあるけど、根源的ではないような気がします。
なぜなら、それらの解答に対して、「人はなぜそれらを求めるのか?」と無限に問い直せるからです。
アンドリュー・ワイルズは、10歳のとき、フェルマーの最終定理と出会い、こう思ったそうです。
「私はこの問題を解かなければならない」と。
その衝動の中に、数学界への貢献とか、物理学での実践とか、そんなものは微塵もなかったはずです。
そこにあったのは、「目の前にあるパズルを解きたい」という、なんの打算もない、どこまでもピュアで子供っぽい知的探究心だったのではないでしょうか。
それは例えば、「3,4,7,8の4つの自然数から、四則演算を用いて10を作れ」と言われ、
思わず(なんの得もないのに)のめり込んでしまうのと同じ知的衝動であるような気がします。
このとき、「人はなぜ知的探究心を持つのか?」と問い直すことに意味はありません。
生物学的な「ヒト」の定義が「ホモ・サピエンス(知恵ある人)」であり、いわば人が知的存在であるのは、数学でいう「公理」にあたるからです。
公理に証明は要りません。それは自明なことなのです。
さて、長々と書いてきて、ちと腹が減りました。
冒頭に顔を覗かせた『フェルマーの料理』が思い出されます。
こちらタイトルとは裏腹に、フェルマーとはまったく関係なく、
「数学的思考でもって料理する」という、ほとんどこじつけのようなコンセプトで描かれます。
評価できるのは、料理を客観的に科学する一方で、
ときには主観も大事であることを打ち出しているところです。
これは僕の食のバイブル『美味しんぼ』でも繰り返し主張されていることで、
万人が納得する「旨さ」を追求するときは客観性を、
個人を感動させる「美味しさ」を提供するときは主観性を重視するという、
料理に対する海原雄山の基本姿勢に見てとることができます。
『フェルマーの料理』──
はたして『美味しんぼ』の後継作品(あくまで僕の中で)となることができるや否や。
最新刊6巻は、明日8/29発売です。