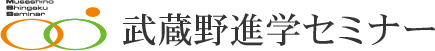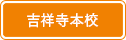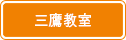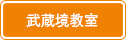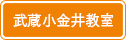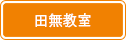わかるとできるの違いについて
こんにちは。吉祥寺校の執行です。
数学や算数を教えているとよく「答えは出せるけれども根本的なことがわかっていないからわかるようにしてください」と頼まれることがあります。
【わからないけれどできる】状態というのは問題の解き方や公式だけを覚えて解いているけれど何をしているのかはわからないという状態です。
算数で言うと,速さの問題をテントウムシ算の図に当てはめて解く方法がそれです。
この【わからないけどできる】方法を嫌う人も多いですが、私は許容派です。
例にあげた速さのテントウムシ算も積極的に使わせます。
何故なら,できるようになってからのほうが【わかる】に至ることが多いからです。
私自身も,子供の頃によくわからないまま使っていた公式の意味があるとき突然わかるようになる瞬間というのを何度か経験しています。
赤ちゃんが言葉をしゃべるようになるのと同じように、算数や数学の内容も理屈ではなく経験によって理解できることがあるようです。
特に小学生や中学1,2年生だとまだ理解力が問題の難易度に追いついていないことが多く、特に国語力の問題で算数や数学の能力とは関係なく問題が解けないことがあります。
その場合は無理にわからせるのではなく【わからないけどできる】状態を目指すこともあります。
できることによって算数や数学を解くのが楽しくなり、数学アレルギーを回避できる可能性が高くなります。
ですから,数学が苦手な方ほど【わかる】より【できる】を優先していくといいと思います。